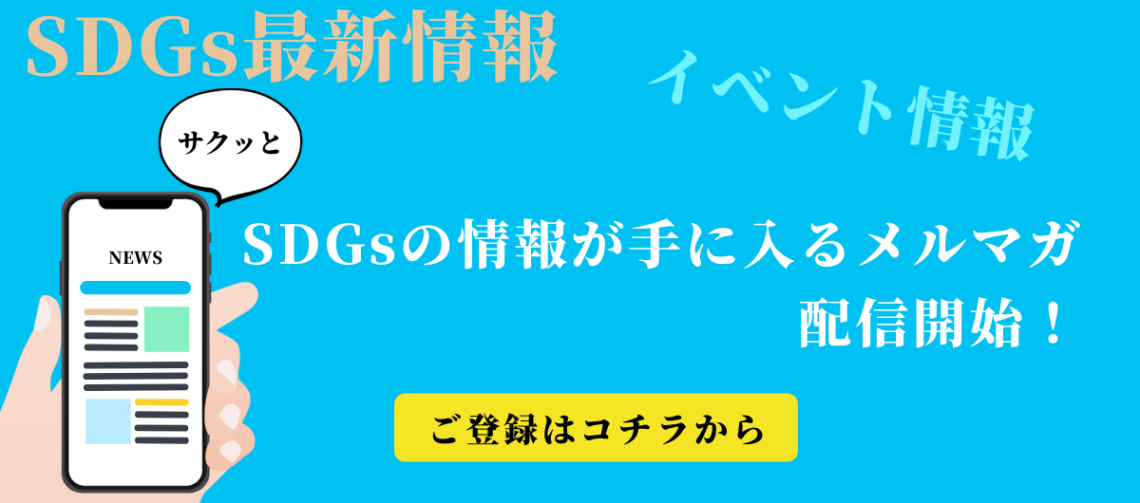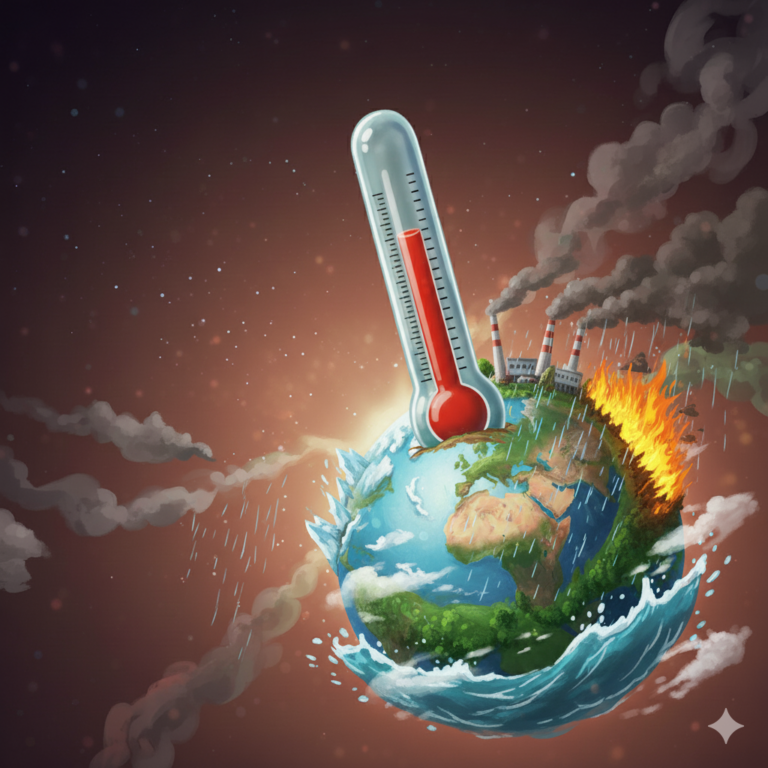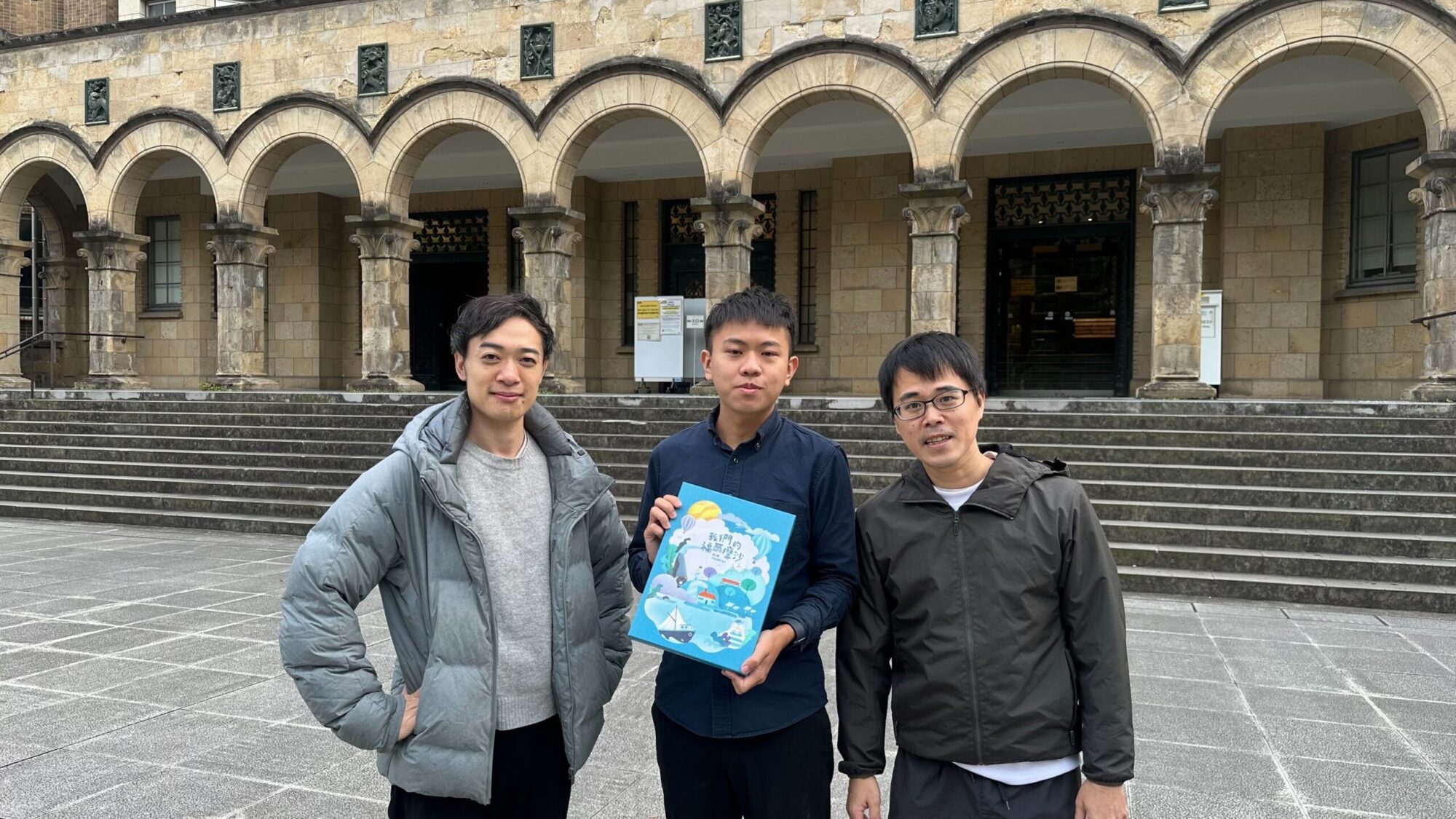ブログ
blogs

「パーパスドリブン」とは?“存在意義”から始まるビジネス(SDGsな旬ワード⑨)
2025/08/03

はじめに
時代の変化とともに、「何のために働くのか」「なぜこの会社が存在するのか」といった問いが、企業や個人にとって重要性を増しています。
近年、注目されているのが「パーパスドリブン(Purpose Driven)」という考え方です。これは、単なる利益追求を超えた“社会的な存在意義”を軸にした経営や行動の在り方を指します。
今回は、企業の変革や個人の働き方にも影響を与える「パーパスドリブン」について紹介します。
パーパスドリブンとは
「パーパス(Purpose)」とは「存在意義」や「目的」を意味します。パーパスドリブンとは、企業や個人が自らの“存在の理由”を明確にし、それを軸に意思決定や行動を行う姿勢を指します。
これまでの経営は「ミッション(使命)」や「ビジョン(未来像)」を掲げることが主流でしたが、パーパスはそれらを土台として、「自分たちはなぜ存在するのか?」という根本の問いに応えるもので、社会課題の解決や共通善の実現と深く結びついています。
なぜ今、パーパスドリブンなのか
背景には、気候変動や格差、孤独、労働環境の問題など、複雑化する社会課題への関心の高まりがあります。特にZ世代を中心に、消費や就職の意思決定において「共感できる目的」や「社会的な意義」を重視する傾向が強くなっており、企業もその価値観に応える必要があります。
さらに、コロナ禍を経て、生活や働き方に対する意識が変化したことで、「自分の仕事は社会にどう貢献しているのか?」という問いを持つ人が増え、企業にも“共感される存在意義”が求められるようになりました。
最新の動向
多くのグローバル企業がパーパスを経営の中心に据える動きを加速させています。たとえば、ある食品企業は「健康を通じて人々の生活をより良くする」というパーパスを掲げ、サステナブルな商品開発と教育支援を両立。一方で、金融やIT業界でも、パーパスに基づいたESG投資やサービス設計が進んでいます。
日本企業の間でも、創業理念を再解釈してパーパスとして再定義し、経営戦略やブランド開発に落とし込む動きが広がっています。特にスタートアップや中小企業にとっては、限られた資源の中で独自性と共感を生み出す“軸”として有効です。
私たちにできること
パーパスは企業だけでなく、私たち一人ひとりにも当てはまります。「自分は何に価値を感じ、どんな社会に貢献したいのか」を言語化することは、キャリア選択やライフスタイルの決定にも役立ちます。
また、共感できるパーパスを掲げる企業の商品やサービスを選ぶことも、社会への小さなアクションとなります。日々の選択や働き方に「自分なりの意味」を見出すことが、持続可能な未来への第一歩になります。
おわりに
パーパスドリブンは、利益と社会貢献を二者択一とせず、両立を目指す新しい価値観です。個人と組織がともに「なぜ、それをするのか?」を問い続けることで、より持続可能で豊かな社会が形づくられていきます。
次回も、注目すべきキーワードを解説を交えてお届けします。ぜひお楽しみに!
学生や社会人の皆さんにとって、今後のキャリアや日々の仕事を考えるヒントになれば幸いです。
《参照記事》
サステナビリティ認証シリーズ一覧はこちら
SDGs業界研究シリーズ一覧はこちら
SDGsな旬ワードシリーズ一覧はこちら
▼本記事シリーズは、メルマガでも定期配信中!
他にもメルマガだからこそ手に入る情報が満載です!気になる方はバナーをクリックしてご登録ください。
《筆者プロフィール》
SDGs/ご当地グルメ/旅行が好きです。その好きなことで仕事をしながら、各地域を盛り上げる中小企業やフリーランスの方々を後押しする活動をしています。