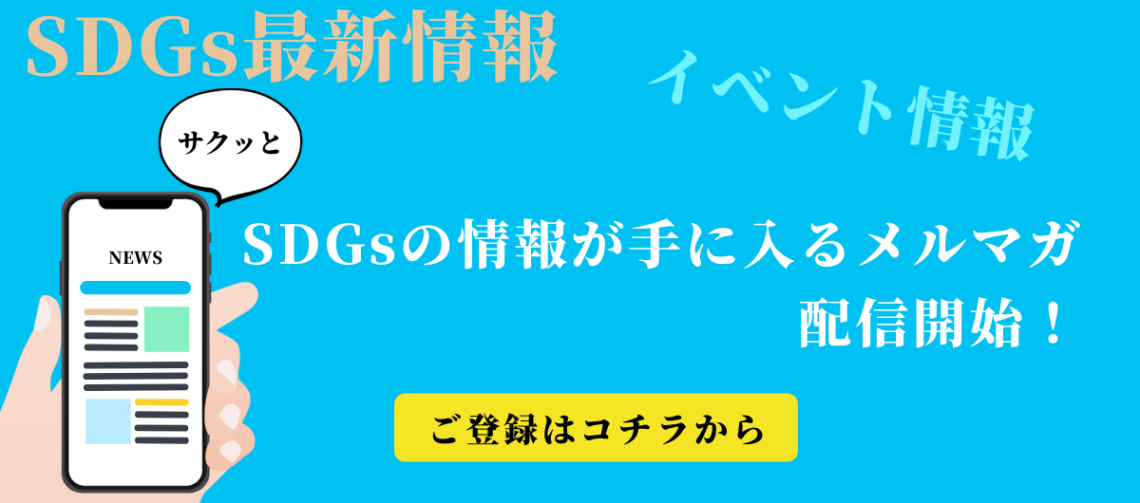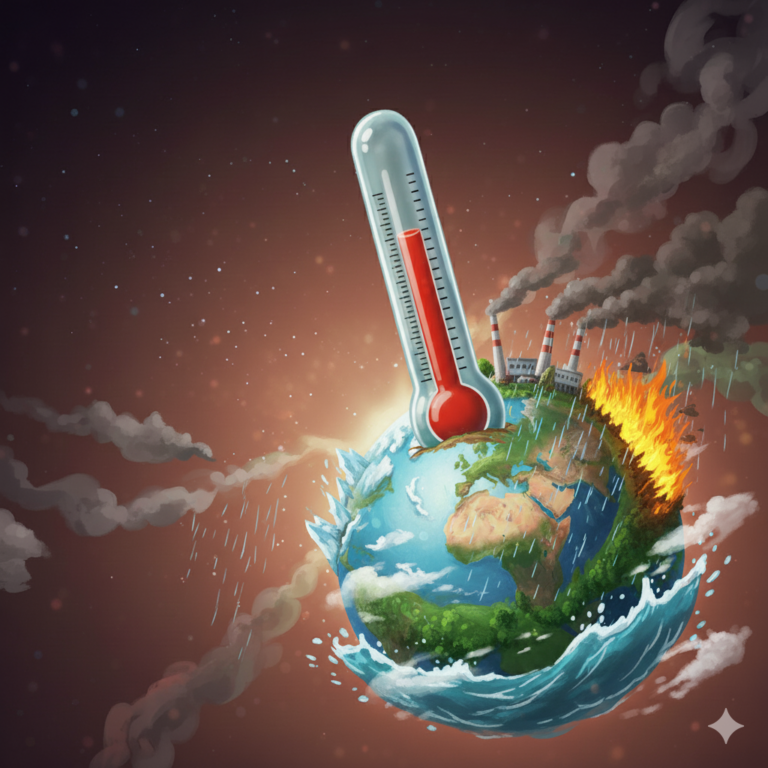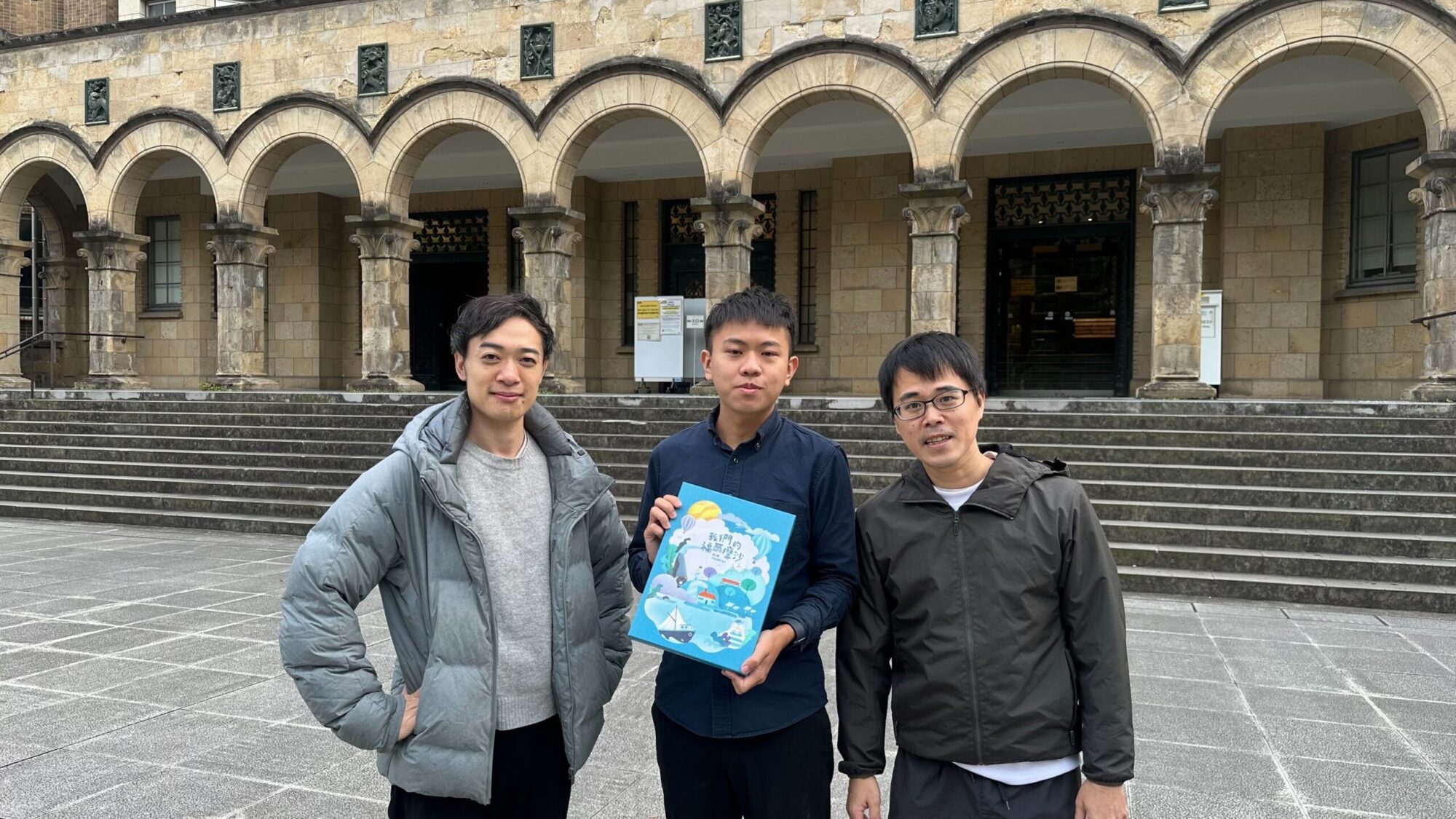ブログ
blogs

捨てない経済「サーキュラーエコノミー」が未来をつくる(SDGsな旬ワード⑥)
2025/04/27

はじめに
「脱炭素」や「サステナブル」という言葉と並び、近年注目が高まっているのが「サーキュラーエコノミー(Circular Economy)」という考え方です。特に欧州を中心に政策や企業戦略として本格導入が進んでおり、日本でも導入の動きが広がりつつあります。
今回は、これからの社会を支える新しい経済モデルとして期待される「サーキュラーエコノミー」について紹介します。
サーキュラーエコノミーとは
サーキュラーエコノミーとは、資源を「採る・作る・使う・捨てる」という直線型(リニア)ではなく、「循環」させることを前提とした経済モデルです。製品や原材料を廃棄せず、可能な限り長く使い続け、リサイクルや再利用、再製造を通じて資源を有効活用することが基本的な考え方です。
従来の大量生産・大量消費・大量廃棄のモデルでは、限りある資源が枯渇し、環境への負荷も深刻化してきました。サーキュラーエコノミーは、それに代わる持続可能な経済のあり方として、有力視されています。
なぜ今、サーキュラーエコノミーが重要なのか?
世界の人口が増え、資源消費が加速する中、原材料の確保がますます困難になっています。加えて、気候変動や生物多様性の喪失、プラスチック汚染など、環境への悪影響も深刻化しており、リニア経済からの脱却が急務です。
サーキュラーエコノミーは、資源の浪費を防ぐだけでなく、経済的な新たな価値創出にもつながると期待されています。たとえば、製品を「売り切り」ではなく「サービス」として提供するサブスクリプションモデルや、廃棄物を原料にしたアップサイクル製品の開発などがその一例です。
最新の動向
EUでは「循環型経済行動計画(Circular Economy Action Plan)」を打ち出し、サーキュラーエコノミーを経済成長戦略の中心に据えています。日本でも2020年に「循環経済ビジョン2020(*)」が発表され、企業・自治体による実証事業や制度整備が進められています。
また、大手グローバル企業の間でも、再利用可能なパッケージの導入や、自社製品の回収・再生プログラムなどが拡大しています。中小企業やスタートアップにとっても、サーキュラーエコノミーは新たなビジネスチャンスを生む切り口として注目されています。
私たちにできること
サーキュラーエコノミーを身近にするために、私たちにできることはたくさんあります。例えば、「使い捨て」を避けて長く使える製品を選ぶ、リサイクルされた素材の商品を購入する、地域のリユースイベントに参加するなど、日常生活の中で循環を意識した選択をすることが第一歩です。
企業や自治体の取り組みに注目することで、私たちも“循環の担い手”として参加することができます。個人の選択が、経済や社会の仕組みを変える力になり得るのです。
おわりに
「サーキュラーエコノミー」は、地球環境の保全と経済活動の両立を可能にする新しい経済モデルです。廃棄物を価値ある資源に変え、無駄のない循環型社会を築くという考え方は、これからの時代を生きる私たちにとって不可欠な視点といえるでしょう。
次回も、注目すべきキーワードを解説を交えてお届けします。ぜひお楽しみに!
学生や社会人の皆さんにとって、今後のキャリアや日々の仕事を考えるヒントになれば幸いです。
《参考URL》
* 循環経済ビジョン2020:https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/junkai_keizai/pdf/20200522_02.pdf
《参照記事》
サステナビリティ認証シリーズ一覧はこちら
SDGs業界研究シリーズ一覧はこちら
SDGsな旬ワードシリーズ一覧はこちら
▼本記事シリーズは、メルマガでも定期配信中!
他にもメルマガだからこそ手に入る情報が満載です!気になる方はバナーをクリックしてご登録ください。
《筆者プロフィール》
SDGs/ご当地グルメ/旅行が好きです。その好きなことで仕事をしながら、各地域を盛り上げる中小企業やフリーランスの方々を後押しする活動をしています。