ブログ
blogs

SDGsトピック「食品ロス」|事例を交えてわかりやすく解説
2025/05/01

SDGs(持続可能な開発目標)は、世界が直面する様々な課題に取り組むために国連によって設定された17の目標で構成されています。前回につづき、目標横断のトピックを取り上げる形で記事を作成していきます。
前回までそれぞれ目標に関して、議題を取り上げてきました。今回から、それら目標横断のトピックを取り上げる形で記事を作成していきます。
現在、人口が世界の人口が急増しており、それに見合うだけの食料の生産が追いつかず、世界全体として食糧難に見舞われる可能性が指摘されています。一方で、食品ロスやフードロスなどの言葉に見られるように、先進国を中心に一部の地域では本来食べられる食品が余っているというのも現状です。
本記事では、食品ロスの概要や具体的な取り組み事例、そしてわたしたちがどのように貢献できるかについて解説しようと思います。
「食品ロス」とは?
食品ロス(フードロス)
まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品のことを「食品ロス(フードロス)」と呼びます。これは家庭、飲食店、食品製造業など、さまざまな場面で発生し、世界的な課題となっています。
食品ロスは大きく以下の2種類に分類されます。
1. 事業系食品ロス
- 規格外品:製造過程で発生する規格外の食品や端材
- 売れ残り:コンビニやスーパー、レストランなどで売れ残った商品
- 返品 :賞味期限切れや返品された食品
- 食べ残し:外食産業や給食施設で提供後に廃棄される食品
2. 家庭系食品ロス
- 食べ残し:作りすぎて食べきれないなど
- 直接廃棄:過剰に購入した食材の腐敗や賞味期限切れ
- 過剰除去:調理の際に廃棄される部分
日本では年間約500万トン以上の食品が廃棄されています。これは、1人あたり毎日おにぎり一個分を捨てている計算になります。食品ロスを削減することは、環境問題の改善だけでなく、食料資源の有効活用にもつながります。
消費者庁, 食品ロス削減ガイドブック(令和4年度版)
食品ロスがもたらす問題
食品ロスが増えると生じる問題が3つあります。
- 環境負荷の増大:廃棄された食品の処理にはエネルギーが必要であり、温室効果ガスの排出を増加させます。
- 経済的損失:食品ロスが発生することで、企業や家庭の経済的負担が増します。
- 食糧問題の悪化:世界では多くの人々が飢餓に苦しんでいる一方で、大量の食料が無駄になっています。
「食品ロス」に関するキーワード
食品ロスを理解するためには、以下の重要なキーワードを押さえておくことが大切です。
賞味期限
賞味期限とは、食品が「おいしく食べられる期限」を示す表示で、適切な保存条件のもとで品質が保たれる期間を指します。主にスナック菓子やインスタント食品、缶詰など、長期間保存できる食品に設定されます。期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありませんが、風味や食感が落ちる可能性があります。一方で、傷みやすい食品には「消費期限」が設定され、安全に食べられる期限を示しています。
流通
流通とは、商品やサービスが生産者から消費者に届くまでの過程を指します。具体的には、輸送・保管・販売・情報伝達などの活動が含まれます。効率的な流通によって、必要な商品が適切な場所・時間・価格で提供され、経済が円滑に回ります。流通には、メーカー・卸売業・小売業などが関わり、近年はインターネット通販の発展により、物流の効率化や流通経路の多様化が進んでいます。
フードバンク
フードバンクは、企業や個人から余った食品を集め、必要としている人や福祉施設、子ども食堂などに無償で提供する活動です。食品ロスを削減しながら、生活困窮者の支援につながる仕組みとして注目されています。賞味期限が近い商品や包装に傷がある食品など、安全に食べられるものが対象です。NPOやボランティア団体が運営し、自治体や企業と連携することも多く、地域の支え合いを促進する役割も果たしています。
子ども食堂
子ども食堂は、地域の子どもに無料または低価格で食事を提供する場です。経済的に困難な家庭の子だけでなく、共働き家庭や孤食が多い子も利用できます。ボランティアやNPOが運営し、食事提供だけでなく地域交流の場としても機能します。近年は高齢者も参加できる「地域食堂」も増え、世代を超えたつながりを生んでいます。
「食品ロス」の主なターゲット
食品ロスについて、関連するゴール・ターゲットをいくつか紹介します。
●目標 1「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」
- 1.1 2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。
- 1.2 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子どもの割合を半減させる。
- 1.4 2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。
- 1.a あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。
●目標 2「飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する」
- 2.1 2030年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。
- 2.2 5歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。
●目標12「持続可能な生産消費形態を確保する」
- 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。
私たち一人ひとりがこのようなターゲットを意識して生活することで、食品ロスの達成に着実に近づくことでしょう。
「食品ロス」の取り組み事例
ここからは、食品ロスに対する取り組みの具体例について、SDGsを楽しみながら学べる「Sustainable World BOARDGAME」の事例をご紹介します。
- 事例1「食と地域をつなぎ神奈川から貧困をなくす」神奈川県版
- 事例2「困っている人に食材を支援する」神奈川県版
- 事例3「貧しい家庭でも購入ができるフードバンクを設置」台湾版
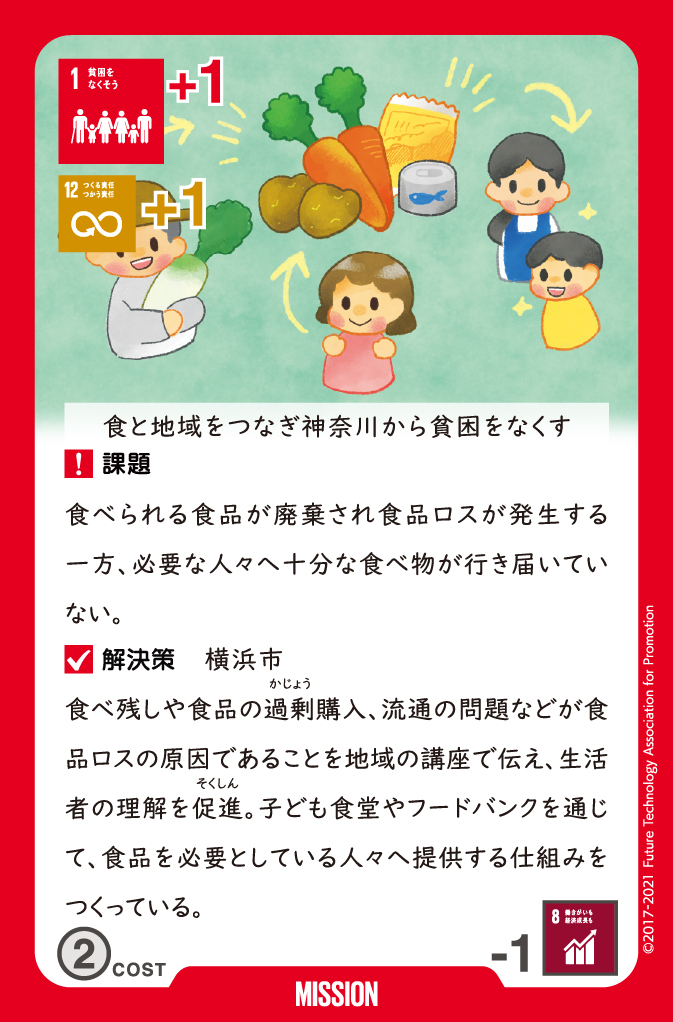
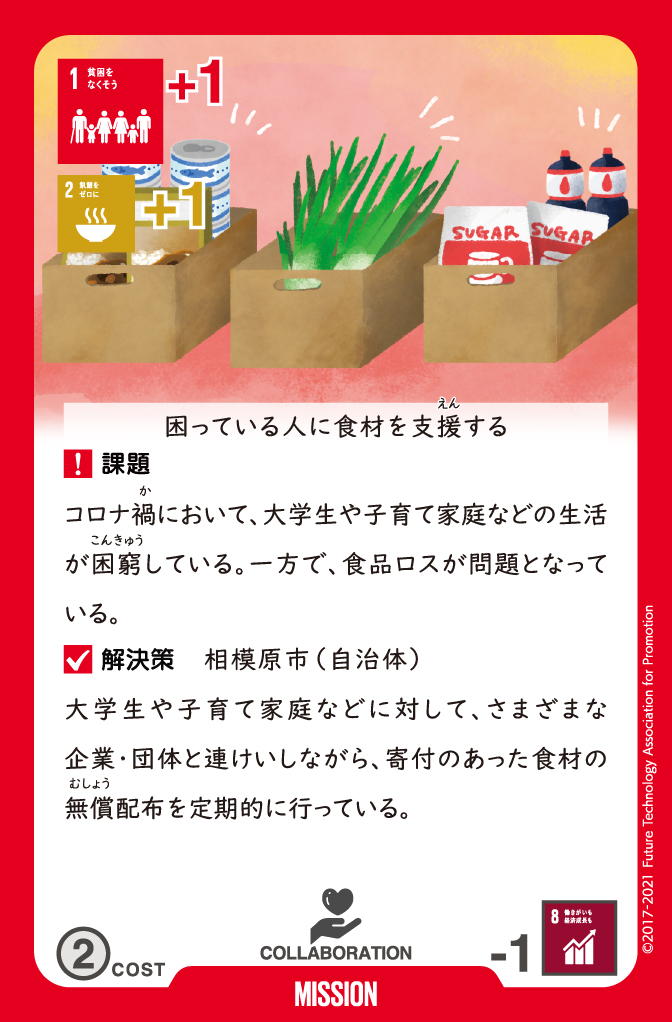
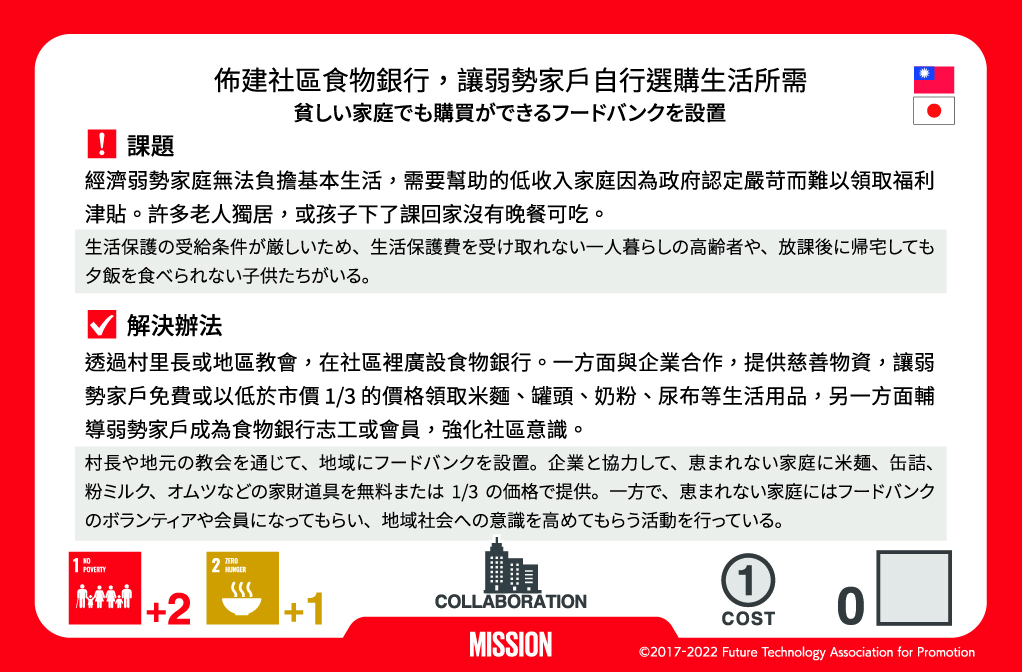
「食品ロス」に対して私たちにできること
これらの活動は、食品ロス削減と食の支援を組み合わせた社会的支援システムの構築を目的としています。特に、食品ロスの発生原因の理解促進と、生活困窮者への効率的な食糧提供に重点を置いています。
- 食品ロスの削減
- 食べ残しや過剰購入の抑制を啓発(記事1)。
- フードバンクや公共冷蔵庫を活用し、不要になった食品を必要な人へ提供(記事2・3・4)。
- 生活困窮者への食支援
- 高齢者、ひとり親世帯、大学生、子どもなど、特に食の確保が困難な層への支援(記事2・3・4)。
- 支援を受ける側も地域の活動に参加できる仕組みを構築(記事2)。
- 支援の利便性向上とプライバシーの確保
- 24時間利用可能な公共冷蔵庫の設置(記事4)。
- 恵まれない家庭が負担なく支援を受けられるフードバンクの整備(記事2)。
- 企業・団体と連携し、定期的な食材配布を実施(記事3)。
最後に
これらの取り組みは、単なる「食品提供」ではなく、持続可能な社会システムの構築を目指しています。食品ロスを削減しながら、地域や企業の協力を通じて、困窮者が支援を受けやすい環境を整えるという包括的なアプローチが特徴的です。




